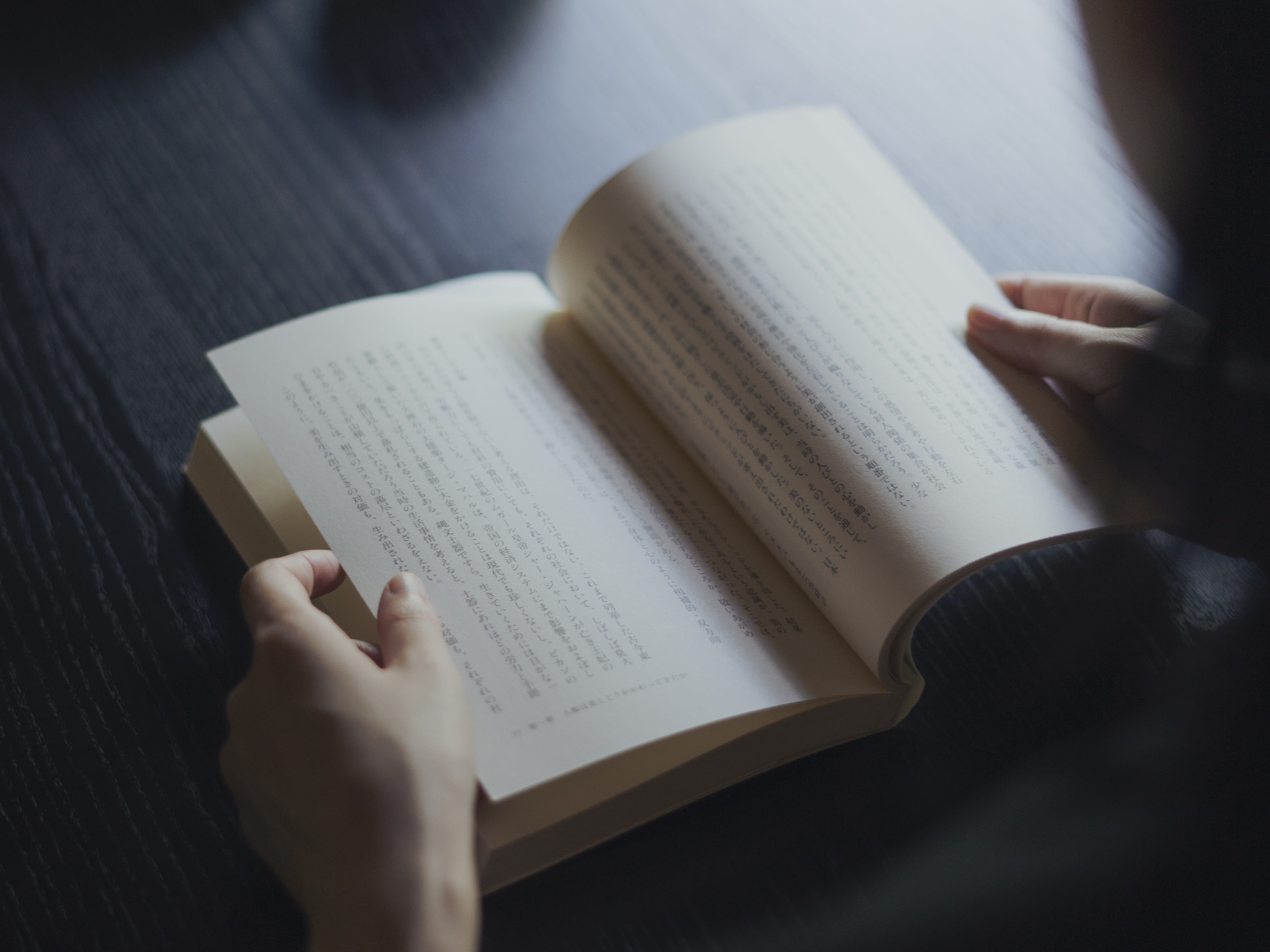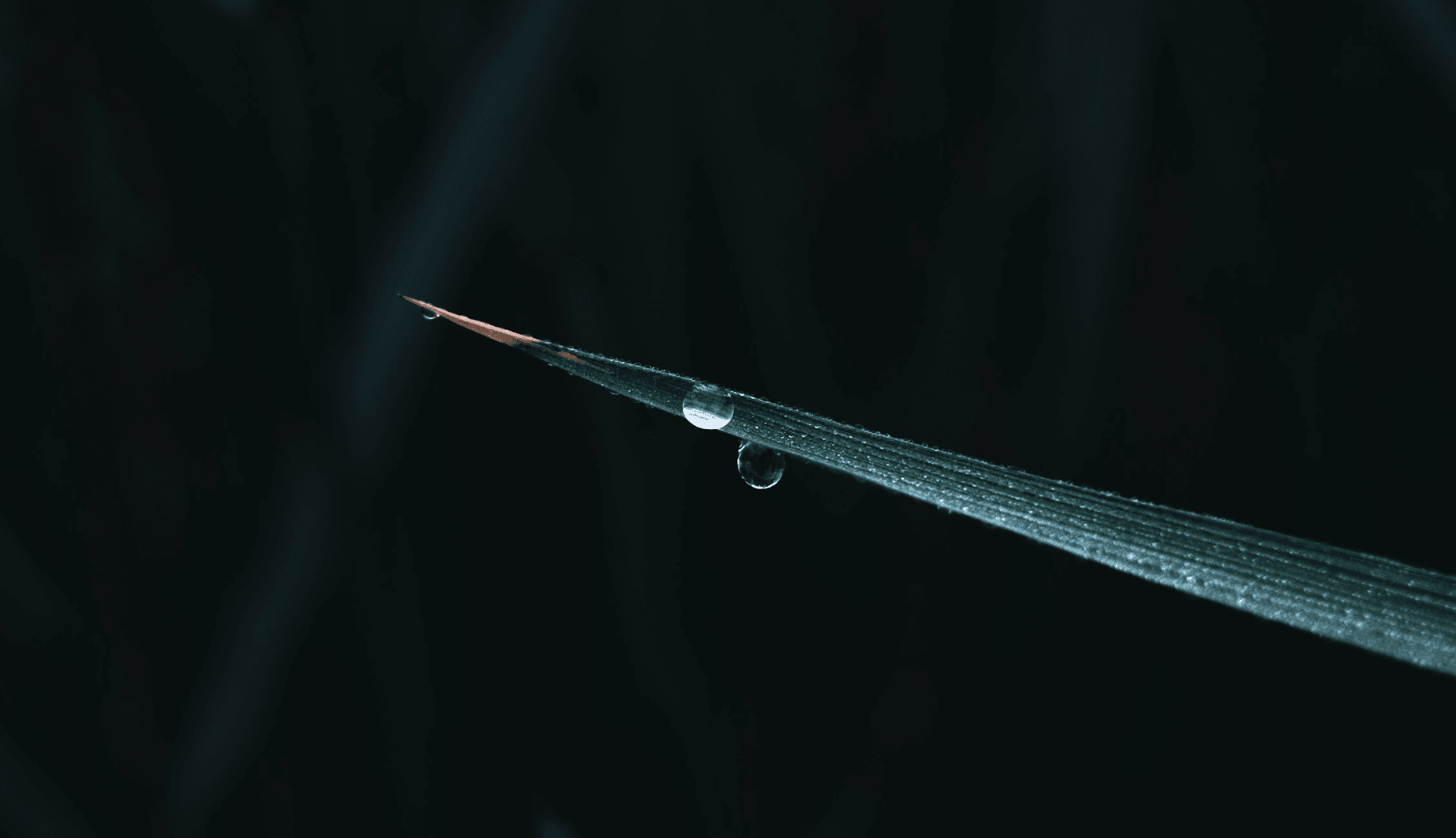FASから新たに誕生したボディケアライン「ザ ドレープ シリーズ」。まるで潤いのヴェールを肌に纏うような心地よさを形にしました。シリーズを象徴するのは、国産繭から生まれたシルクエキス。シルクは、人の肌と同じアミノ酸構造をもつ、もっとも人に近い天然のタンパク質といわれています。そのため、肌にすっとなじみ、潤いを留める力にすぐれています。保湿・明るさ・ハリに多角的に働きかけ、まるで一枚の上質な布を纏うように、大人の肌をやわらかく包み込みます。
日本の素材をスキンケアへ
わたしたちのものづくりは、日本の風土から生まれた原料を探すことから始まります。 どこで、どのように育った素材なのか——。 その背景を知り、土地や自然と調和して育った素材を選ぶこと。それがFASのものづくりの原点です。 日本の風土で育った素材は、わたしたちの肌にも自然になじむ。 その確信があるからこそ、シルクも、その背景が見える国産繭から生まれたものを使っています。

衰退する日本の養蚕業
とはいえ、国産の繭を選ぶことは決して簡単なことではありませんでした。 養蚕業は年々縮小を続け、全国の生産者は100軒を切るともいわれています。 もともと蚕は非常に繊細な生きもの。 水に濡れるだけでも命を落としてしまうほどで、温度や湿度の管理など、熟練の手と勘が欠かせません。 桑の葉を使う昔ながらの飼育方法では、養蚕ができる時期が桑の葉が採れる5月から10月に限られ、 猛暑の影響で夏の飼育も年々難しくなっています。 さらに、機械を扱うメーカーの廃業などにより、手作業の負担が増えているのが現状です。
養蚕を取り巻くこのような厳しい状況の中、納得のいく国産繭を育てている生産者に出会うことは、まるで細い糸の先をたどるような試みでした。何度も断られ、そのたびに途方に暮れそうになりながらも、国産繭を諦めるという選択肢は、わたしたちにはありませんでした。途切れそうな糸を決して手放さずに進み続けた先で、ようやく信頼できる一軒の生産者と出会うことができたのです。
養蚕農家の多くが絹糸として出荷する中で、その生産者は「肌にのせるための繭づくり」に真摯に向き合っている方々です。飼育環境や管理の過程も丁寧に共有してくださり、実際に現地を訪れて、その誠実な手仕事に深く心を打たれました。信頼できる生産者と素材に出会えたことが、この「ザ ドレープ シリーズ」にとって確かな手応えと希望を感じる大きな一歩となりました。
静岡で育まれる国産繭
国産繭を生産している静岡県のとある農業法人を訪ねたのは、 主力商品でもある枝豆がちょうど収穫の時期を迎えた頃でした。 畑には、太陽の光をたっぷり受けて、ぷくぷくと膨らんだ枝豆がすずなりに実り、 土の匂いとともに、この土地の豊かさを肌で感じました。 養蚕を担当するその方は、大の昆虫好きで、大学では生物多様性について研究していたのだとか。今もトンボの保全活動に取り組む“トンボ博士”でもあります。 最初はおひとりで蚕の飼育方法の研究を始めたのだそうです。 「蚕の幼虫は生まれてから約1ヶ月の間に4回脱皮をして繭をつくるのですが、 繭をつくる直前の蚕さんは大きく成長していて、とてもかわいいんですよ。 桑の葉を食べている姿も本当に愛らしいんです」 “蚕さん”と呼ぶその口ぶりからは、 小さな命への深い愛情が滲むように伝わってきました。

”間口を広げる養蚕”という挑戦
彼らが目指しているのは、かつての養蚕を復活させることではなく、養蚕の衰退に歯止めをかけ、持続可能な形で次の世代へつなぐこと。従来の養蚕は体力勝負の重労働で、「10年やらないとよい繭はできない」と言われるほど熟練を要します。その障壁の高さが新しい人の参入を難しくし、結果として養蚕の衰退を加速させてきました。
だからこそ、“間口を広げる養蚕”に取り組んでいるのだそう——。
蚕は桑の葉を食べて成長します。そのため養蚕農家では、桑の葉を摘むことも大切な仕事のひとつ。蚕が大きくなると、たくさんの桑の葉を食べるので1日に3〜4回新しい葉を与えます。蚕は濡れた葉を食べると命を落としてしまうほど繊細なので、雨の日には一枚一枚、葉の水分を拭き取ってから与えるのだそうです。天候に大きく左右され、ときに厳しさを伴う——それでも、自然の力と向き合い続ける仕事です。
そんな養蚕の過酷さを、少しでもやわらげ、持続しやすくするために、こちらの農業法人では桑の葉に自社で育てた野菜を混ぜた、独自の飼料を開発しました。 天候や季節に左右されず、安定して繭をつくれるように——。蚕の“好み”を知るために、さまざまな野菜を試しながら実験を重ねたといいます。「蚕さんは甘いものやタンパク質が豊富なものを入れることで、よく食べ、よい繭を作ってくれます。枝豆はタンパク質も豊富で、繭をつくる力を支える重要な栄養源になりますし、さつまいもは餌を食べやすくする手助けもしています」


蚕にも、人にもやさしい畑
一方で、蚕はその繊細さ故に農薬にも非常に弱く、ごく微量でも反応してしまうほど敏感な生きものです。つまり、この畑で育つ野菜は、蚕が健やかに育つほどに、やさしく安全な環境でつくられているということ。蚕が好む枝豆は、農薬もほぼ使わず、ほとんどを手作業で育てています。雑草も除草剤を使わずにすべて手で抜いているので、夏の除草作業はとても大変です。でも、それだけ手塩にかけて育てた枝豆は皮ごと飼料にできるほど蚕にとって安全。それは、繭を育てることと、食物を育てることが、別の営みではなく、どちらも“いのちを育てる”という一点でつながっているということでもあります。
蚕がいちばん自然に成長できて、作業する人が特別な知識や体力を必要としない。誰もが、どこでもできる養蚕を目指して。この農業法人では、農業と福祉をつなげる「農福連携」にも視野を広げ、福祉施設の方々でも取り組めるようなマニュアルづくりも少しずつ進めているそうです。伝統を守るだけでなく、未来へつなぐ。彼らの養蚕には、そんな静かな挑戦の姿勢が息づいています。

素材の向こう側を見つめて
蚕が安心して育つ環境から生まれた繭だからこそ、 いうまでもなく、人の肌にもやさしい。 だから、わたしたちはこの国産繭にこだわりました。 肌にのせるものは、成分だけでなく、その背景までもクリアでありたい。 その透明性と誠実さこそが、FASがものづくりの中で大切にしていることです。
彼らのような思いを持って育てられた国産繭を使ってスキンケアをつくることが、養蚕の衰退にほんの少しでも歯止めをかける力になれば——。 そんな願いも静かに込めています。
化粧品ブランドが本来ここまで語る必要はないかもしれません。それでもわたしたちは、素材の向こうにいる人や自然の姿を、まっすぐに伝えたい。知ることで、選ぶ基準が変わり、その選択が、誰かの手を支えることにつながっていく。そう信じて、FASは今日も、一つひとつを丁寧に紡いでいます。