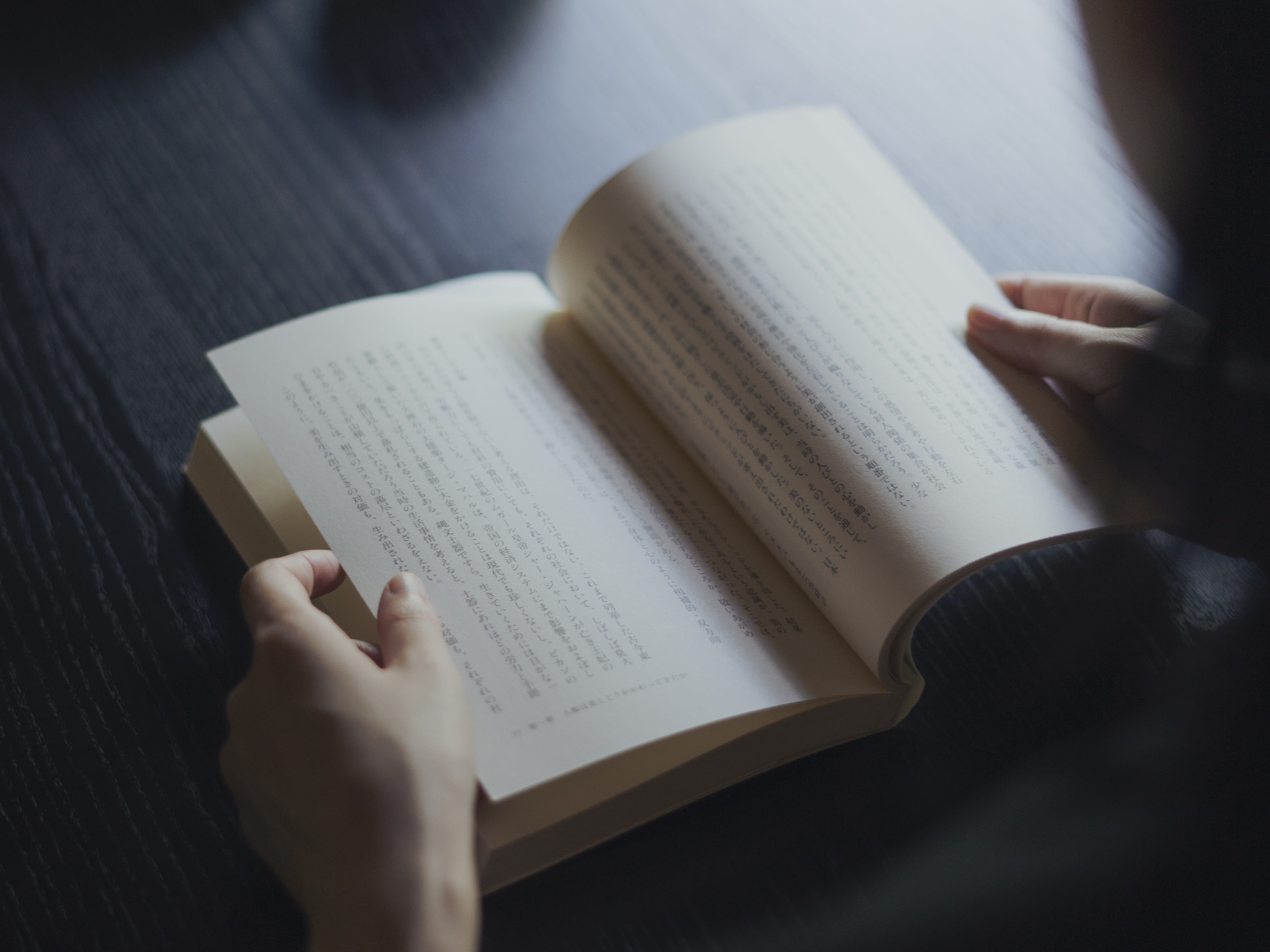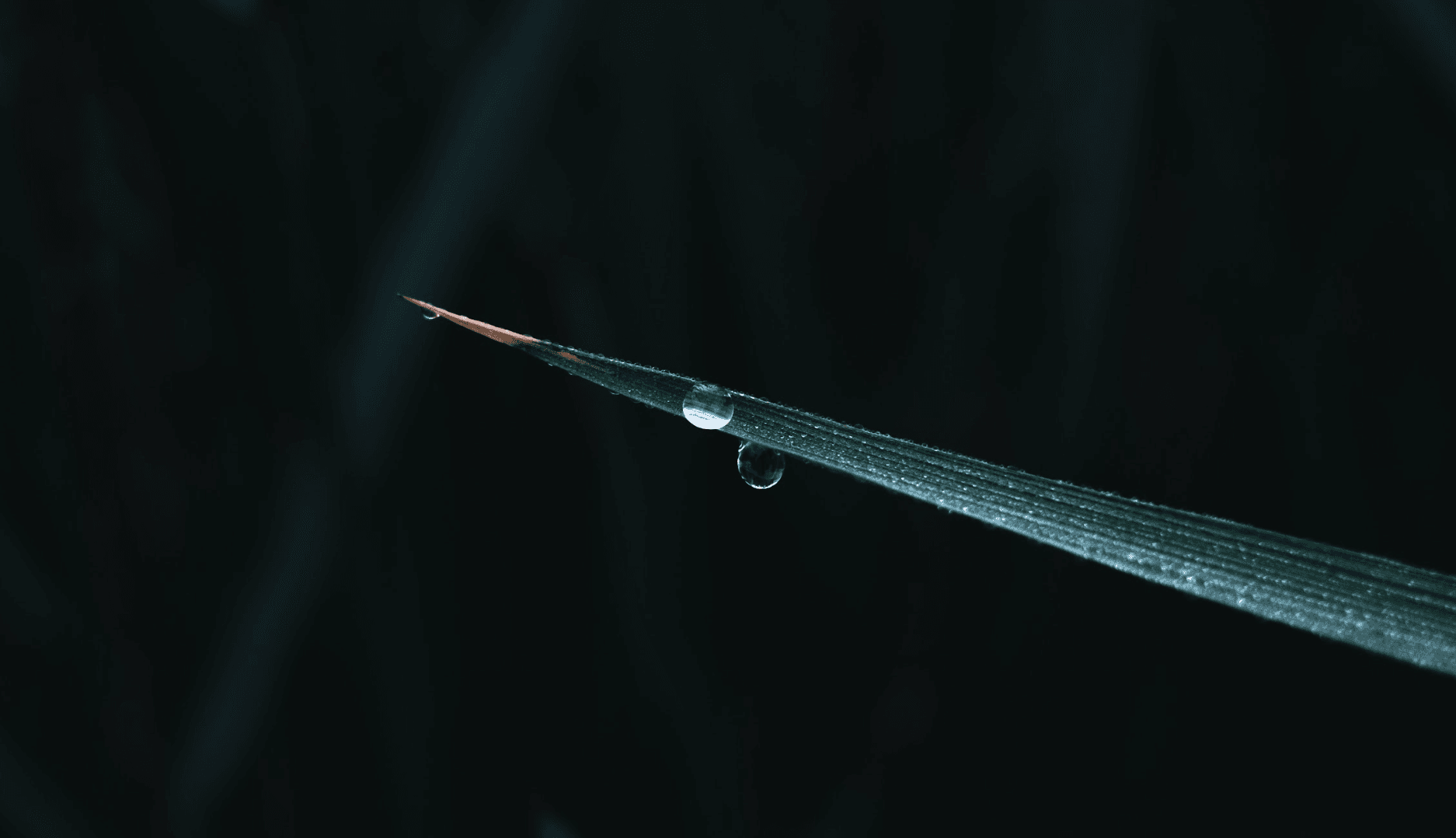佐々木1日1組限定の宿「民宿とおの」そして、和のオーベルジュ「とおの屋 要」を営んでいる佐々木要太郎です。発酵料理人としての肩書きの傍ら、米農家として米「遠野一号」の自然栽培を続け、その米を使ってどぶろくをつくる醸造家としても活動をしています。
ーーーー江戸時代から続く武士の家系に生まれ、100年余り続いてきた「民宿とおの」の思想を4代目として継承する。料理の基礎を父から学んだ後、独学で料理を極め、その傍らでどぶろくづくりを始める。そして10年以上の試行錯誤を経て国内外で絶賛されるどぶろくを製造している。
向山ありがとうございます。米をつくり、どぶろくをつくり、料理をつくる。食材の栽培から加工、そして提供まで。一貫してそこまでやられている方は、なかなかいらっしゃらないですよね。国内外で注目をされている佐々木さんのどぶろくですが、そもそもどぶろくづくりに興味をもったきっかけを教えていただけますか。
佐々木2002年、離婚を機に遠野に戻ると、父から「遠野市が日本初の『どぶろく特区』になる」と。父がどぶろく特区の発起人だったのもあり、免許申請をやってほしいと頼まれたのがきっかけです。父はおそらく事務要員として僕にお願いしたと思うのですが、実際に講習会にいったらどぶろくや発酵の魅力にどっぷりハマってしまって。どぶろくのつくり方って、日本酒と同じ並行複発酵っていう発酵のさせ方なのですが、これって世界で日本だけの技術なんです。
ーーーー並行複発酵は『糖化』と『発酵』を一つのタンクで同時進行で行う発酵方法。ビールなど単行複発酵は『糖化』と『発酵』を2つの工程にわけることでアルコールと炭酸を生み出す。
向山菌の働きによって生じる現象。その結果が人間に有益であれば『発酵』、人間に有害であれば『腐食』というように一般的には定義がされていますが、お酒づくりを通して発酵と向き合ってこられた佐々木さんは『発酵』というものをどのように捉えていますか。